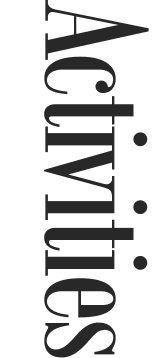
[ 武井祥平・高橋琢哉インタビュー① ]
―― 想像力と創造力を喚起する風景
WORK with ART Project 開発ストーリー

解釈の余白を生み出す場づくり
―― ミュージアムタワー京橋の1階から3階にかけてのエスカレーター空間、そして3階オフィスラウンジに展開されるアート作品において、武井さんは監修を務められました。植栽や音楽といった作品をとおして、訪れる人にどのようなことを働きかけているのでしょうか。
武井祥平(以下、武井) 「WORK with ART」というビルのコンセプトから私が想起したのは、人間の想像力/創造力を喚起する場の必要性です。与えられた環境を享受するだけではなく、自分なりの使い方や意味を見出していけるような余白を生み出したいと思いました。
―― フロアでの過ごし方を複数設け、それらを柔軟に選択できる仕掛けがあることを、空間デザインを手がけたI IN(アイイン)さんにうかがいました。
武井 空間の中心に植栽を位置付けたいというデザインの方針があったなかで、その植栽がどのような意味を持つべきか、また、訪れる人が目にするもの、耳にするものとどのように融合してビル全体の印象につながっていくのか。そのような視座を持って、ここにあるべき音の風景を一緒につくっていけるパートナーが高橋さんです。

―― 高橋さんの楽曲制作における場の捉え方について教えてください。
高橋琢哉(以下、高橋) どのような音をつくるかよりも、どのような場をつくるかということを起点に構想を始めます。どういう人がなんのために、どれくらいの時間とどまるのかと理解を深めていくなかで、空間そのものを体感できる音楽のあり方を探っていきます。屋外の舞台演出においても、美術館や博物館の空間演出においても共通するアプローチです。

さまざまな聞こえ方を促す音楽
―― 植栽と音楽をとおして、このオフィスラウンジもまた、ミュージアムタワー京橋のモチーフになっている「武蔵野の森」を体感できる場になっています。
高橋 特定の意図を伝えるような「聞かせる音楽」ではなく、毎日聞いていても心地良くその場にとどまっていられる、自然としての音楽で空間を包みたいと思っていました。当初はフィールドレコーディングによる本物の自然音を使うアイデアがありましたが、それでは生っぽさや音のディティールが強く表れてしまい、いかにも自然らしいという印象を押し付けることになってしまう。この場で目指しているのは、いろんな聞こえ方や受け取り方を促すための余白をつくることです。そのため、フィールドレコーディングよりも抽象度の高い音楽をつくる必要がありました。