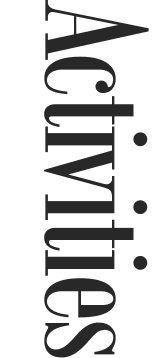
[ 高谷史郎インタビュー① ]
―― 地球の姿を映したパブリックアート
WORK with ART Project 開発ストーリー

「地球とは何か」を問うとき
―― 2024年秋にミュージアムタワー京橋の1階エントランスロビーに設置された作品《WINDOWS》。本作が生まれた背景について教えてください。
高谷史郎(以下、高谷) この世界や地球全体に向けて「窓」を開いて、いろいろなものを見る。そしてそれらの窓から風が吹き込んでくるというようなイメージから、構想を練っていきました。

―― 2023年にアーティゾン美術館で開催されたヴェネチア・ビエンナーレ帰国展※がきっかけになっているとうかがいました。
高谷 2022年のヴェネチア・ビエンナーレの日本館展示に選出されたときは、コロナ禍による移動制限などの影響から、「世界の風通し」が悪くなったとでもいうような感覚を持ちながら日々を過ごしていました。作品の構想に悩むなか、Dumb Type(ダムタイプ)のメンバーのひとりが1800年代のアメリカの地理の教科書を持ってきたんです。「What is geography?」というテキストから始まるそれには、地球とは、大陸とは、海とは何かといった、現代にも通じる問いが綴られていて。もし未来から人がやってきて「地球とは何か」と問うたら、私たちはどう答えられるだろうかと考えるようになりました。そこからパフォーマンスやインスタレーションといった作品をつくり、今回のパブリックアートまで展開を続けてきました。
―― 作品世界に鑑賞者を誘うような映像と音楽が印象的です。
高谷 映像は、インターネット上に公開されている世界各地のライブカメラの映像をベースにしたものです。現代では一般家庭に付いている監視カメラの映像までパブリックになっていたりする。世界中のそのような映像を収集することで、「地球とは何か」という問いへの答えが見えてくるのではないかと思いました。宇宙や人工衛星から地球を俯瞰するのではなく、私たちと同じ目線で地表を張り巡らせている実際の映像から、地球を表現できないかと。

世界中のライブカメラとつながる「地球儀」
―― このビルのオフィスで働く人々だけでなく、ビルの外を通る人、窓越しに目にする人にも向けた作品でもあります。
高谷 「四角い地球儀」とでもいうような、両面それぞれが地球の裏表を表しています。太陽の動きや地球の回転を感じとれるように、ライブカメラの映像を緯度・経度順に配置しています。
―― 映像はどのような周期で切り替わるのですか?
高谷 実際の1日(24時間)を24秒で表していて、2~3日分の様子を映した後にシーンが切り替わるようなかたちです。画面の構成(分割数)も変動的なので、地球を捉える縮尺も変化していきます。

―― 同じ映像は二度と見られないのでしょうか?
高谷 はい。世界中の映像を今この瞬間もコンピュータがダウンロードし続けていて、作品は毎日更新されています。眺めていると、地球規模での季節の移ろいも捉えられるようになります。
―― 8つのスピーカーから流れる音楽についても教えてください。
高谷 地球の回転を想起できるようなオリジナルサウンドをベースとしつつ、インターネットから収集可能なラジオや環境音のデータ、また先述の「What is geography?」という言葉をコンピュータが朗読した音声などをミックスして構成したものです。地球儀でもあり、窓でもある。「世界につながる窓」というコンセプトが作品全体を包んでいます。
※「第59回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館展示帰国展 ダムタイプ|2022: remap」 https://www.artizon.museum/exhibition/detail/555