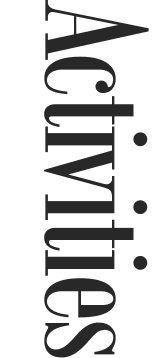
[ 山口 周インタビュー③ ]
―― 知的生産の第一歩は、環境の機微を感じ取ること

「変化するアート」が側にある意味
―― ミュージアムタワー京橋(以下、MTK)の1階から3階をつなぐエスカレーターには「気分の変容」をテーマに創作された音楽作品が流れています。また3階ロビーは「心身の整調」というテーマのもと、武蔵野の森をイメージした植栽や照明と共に音響空間がデザインされています。

山口 周(以下、山口)3階ロビーに広がるサウンドスケープは、私の仕事場にもあったらいいなと思いました。というのも、執筆や読書といった精神活動において、具体的な歌詞やメロディーを伴った音楽は存在感が大きすぎるんですね。意味性が強く、脳のキャパシティーが占有されてしまうんです。葉山にある私の自宅でずっと聞こえているのは、雨や風、波などの自然音。これらを全身で感じながら、精神を整えています。
―― 働く人の感性や創造性を刺激するために、自然やアートを取り入れるオフィスも増えています。
山口 変化が無く情報量の乏しい環境で毎日働くということは、人間にとって不自然な状態です。一方で、アートは人間がつくった自然である、と言うことができます。変化の少ないオフィス空間に感覚を揺さぶるようなものを入れ込むのは、意味のあることでしょう。
MTKではそのことをかなり意識的に、外部環境の変化を反映するようなダイナミックな作品をキュレーションしていますよね。ダムタイプのパブリックアートは、世界中にあるウェブカメラの映像や、地層や天候といった自然界の情報を組み合わせて自動的に生成しているとのことですが、そうした「変化するアート」を通して人間の五感や認知を刺激し、覚醒させる。作家がそういうことを考えたのかはわかりませんが、私の問題意識からすると、これはオフィスビルの新しいソリューションであるという気がします。
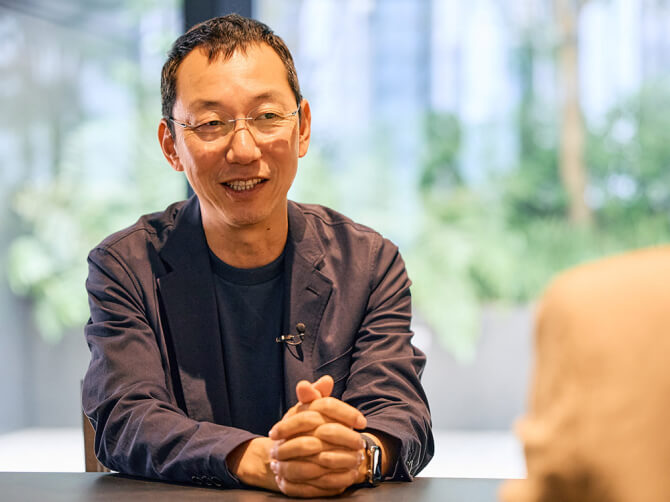
美意識から始まるウェルビーイング、そして社会資本へ
―― なぜ、五感や認知を刺激することが大切なのでしょうか。
山口 葉山に住んでいると、日ごとに異なる海の表情、天候や季節と共に移り変わる山の景色を感じることができます。フランスの画家、ポール・セザンヌが同じ山(サント・ヴィクトワール山)をたくさん描き続けたのは、ひとつとして同じ風景は無かったから。
人間の脳が今のように進化したのは10〜20万年前と言われています。刻々と変化する自然環境に適応し、危険を察知するためにあらゆる神経を研ぎ澄ませてきました。外部の微細な変化やちょっとした情報を捉えて、それに対応できるセンシティビティの高い人間が生き残ってきたわけですね。

現代であれば、日々の生活から社会の動きまで、さまざまな変化を上手に捉える人がビジネスで成功を収めています。これからますます予測不可能な社会になっていきますから、ある種の集中力をもって世の中の変化を見る、聞く、感じるということを意識的にしていかないと、成長を続けることは厳しい。また、それこそが知的生産の第一歩であると思います。
―― 働く場所に限らず、日々の生活を取り巻く環境から受ける影響も大きいのかもしれません。
山口 ヨーロッパの都市、パリやフィレンツェなどは、街自体が美術館のようですよね。その国の美意識が圧倒的な密度で蓄積されていて、かつパブリックに開かれています。都市の空間や施設そのものが人の美意識を刺激し、鍛えるのです。これは社会資本と呼ぶべき重要な存在になっていると思います。
そういう意味では、世界的に見て日本は不利な状況にあります。明治時代に外国人が日本にやって来たときに「なんと美しく清潔な街だ」と驚いたという、江戸の美しい街並みや景観が今やまったく残っていないわけですから。自分たちが持っていた文化や伝統をすべて壊して、コンクリートで「近代化」してしまった。限定的に保存されている地区もありますが、ほとんどは断絶してしまいました。日本は美意識を鍛える、育てるという社会資本の部分がとても弱いので、これからの100年をかけて取り組んでいかないといけません。
―― 美意識という社会資本を築いていくうえでは、どのようなアプローチがあるのでしょうか。
山口 単純に美術館に来てもらうというよりは、むしろアートが街の外に出ていく努力をしたほうがいい。19世紀の思想家・デザイナーであったウィリアム・モリスが提唱した「生活の芸術化」、あるいは昨今のウェルビーイングにつながるのかもしれませんが、日常的に触れる場所をいかに豊かで美しくしていくかということだと思います。