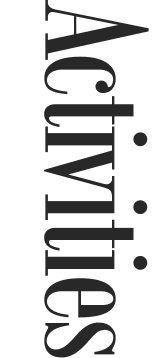
[ 山口 周インタビュー④ ]
―― 「コミュニティの回復」の鍵は会社にある

日本が培ってきた社会秩序の価値
―― これからのオフィスの役割についてはどのようにお考えですか。
山口 周(以下、山口)ひとつの考え方として、「コミュニティの回復」ということが挙げられます。具体的には、仕事のコミュニティ、趣味のコミュニティ、そして地域コミュニティを見直すということです。今、シリコンバレーではキリスト教が一種のブームで、ロンドンでも教会に行く若者が増えているそうです。欧米の人たちにとって教会というのは最後のコミュニティなんですね。
―― 働く人の感性や創造性を刺激するために、自然やアートを取り入れるオフィスも増えています。
山口 変化が無く情報量の乏しい環境で毎日働くということは、人間にとって不自然な状態です。一方で、アートは人間がつくった自然である、と言うことができます。変化の少ないオフィス空間に感覚を揺さぶるようなものを入れ込むのは、意味のあることでしょう。
そこで私は、日本においては会社という場所がコミュニティの拠点になると考えています。日本では昔から従業員を解雇せず、またインフラや生活水準は維持され、治安も良いとされてきました。先進国のなかで経済成長率という点では劣っているかもしれないけれども、今改めて海外から「いったいどうやって社会秩序を維持しているのか」と関心が高まっているんです。

―― 会社が担う役割は、経済的なものだけではないのですね。
山口 私は日本の会社に長く務めた後に、外資系企業に移りました。今でもその時のことをよく覚えていますが「何か大事なものを持っていたのに、それに気づかないまま手放したんだ」という感覚がありました。日本の会社における従業員の心理的安全性というのは、欧米企業からは想像できないものだと思います。
話を戻すと、これからの日本社会にとって避けては通れない孤独という課題を乗り越えていくうえでも、日本独自のコミュニティのあり方をつくっていく必要があります。さまざまな場所で人間関係が希薄になっていったときに、会社という場所が鍵になる。従業員のエンゲージメントに悩む企業が、現代にこそ、「あなたの家族は会社なんだよ」と言い切ってしまうのもひとつの手かもしれません。
コミュニティとしての会社の役割を高めていく
―― 欧米では、家でも職場でもないサードプレイス(第三の居場所)としてのカフェや公園の価値が注目されてきました。日本において、そのようなサードプレイスに求められている安らぎやつながりを会社が提供するうえでは、自宅やオフィスの立地も大きな要素になってきそうです。
山口 その議論もあるでしょう。例えば熱海や小田原など、東京に1時間前後で通うことができて、少し足を伸ばせば豊かな自然もあるという場所に移住する人が増えているようです。オフィスや家がいろいろな場所にあって、その時々で使い分けていくようなスタイルもあり得ると思います。
サンフランシスコではいまだに出社率が3割くらいで、社員がなかなか会社に戻ってこないそうです。スキルのあるワーカーは市場価値が高いため、無理に「会社に来い」と言おうものならすぐ転職してしまいます。なんとか会社に来てもらおうと美味しいカフェテリアやスポーツ施設をつくったりして、競争力を確保しようと各社工夫を凝らしているのです。
―― わざわざ時間をかけてでも通いたいと思ってもらえるオフィスについて、日本企業もさまざまに試行錯誤を重ねていると聞きます。
山口 約20年前に電通本社ビルが建設されたとき、社員だった私は「お風呂とサウナのあるオフィスが欲しい」と言いました。今ではサウナ付きのオフィスも増えているので、当時としては先見の明があったと思うのですが(笑)。
日本の都心では、多くの人は毎日の通勤に往復2時間ほどかかっていると言われます。その時間を1年間、楽器や語学などにあてたら、大概のことは習得できてしまいますよね。人生が変わってしまうかもしれない。そうした機会利益を投げうってでも会社に来てもらうには、よほどの理由がないといけません。
―― 魅力的な設備やコンテンツと同じく、オフィスでどんなミュニケーションが生まれるかといったことも重要な指標になりそうです。
山口 ある調査会社によると、従業員のエンゲージメントを高める要素のひとつが「褒められる」ことだそうです。特定の目的で集まったオンラインミーティングでは、通りがかりに「あのプレゼンよかったよ」と声をかけるチャンスがありません。またもうひとつの要素は「職場に親友がいる」こと。なんとなく馬の合う人と、示し合わすわけでもなくたまにランチを一緒にするといった体験は、会社に来なければできないことです。
日本において会社という枠組みが欧米以上にコミュニティとしての役割を果たしてきたことを考えると、その機能をより高い次元で維持していくためには、どういった物理空間やロケーションがいいのか。そういう視点でこれからのオフィスのあり方を考えてみると、いろいろなアイデアが出てくるのではないでしょうか。

―― そのような物理的な空間やコミュニケーションを支えるものとして、先ほどおっしゃっていた美意識が根底にあるといったような全体像が見えてきました。
山口 社会や経済が成熟した時代において、人々は「心の豊かさ」を求めているということ。ビジネスパーソンの教養や美意識が社会に大きな影響を与え、これからのビジネスが社会彫刻としての側面をますます増していくということを伝えたいです。
特に東京など都会においては環境から伝わる情報が極端に少ないため、そこで働く人にこそ、自らの五感を揺さぶり、感性を鍛えていくような努力や仕掛けが求められるでしょう。そのひとつの手段として、自然と近い情報量をもつアートに日常的に触れていく。その可能性について考えてみて欲しいと思うのです。