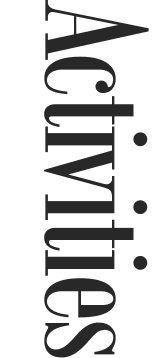
[ 高谷史郎インタビュー② ]
―― 「世界とつながる窓」から吹き込むリアリティ
WORK with ART Project 開発ストーリー

変化し続けるアートの力
―― 《WINDOWS》が設置されているのは、ミュージアムタワー京橋のオフィスフロアのエントランスロビーです。日常をとおして本作を鑑賞することになるオフィスの方々に、アートはどのような影響を与えると思いますか?
高谷史郎(以下、高谷)アートというものは、ものすごく不器用なコミュニケーションの方法だと思っています。人間が持つ感情の深いところにタッチできる一方で、そのことがどんな影響を与えるかはわからない。鑑賞者の心身の状態に左右されるからです。ただ、《WINDOWS》が映す、次々に切り替わる世界中の映像をとおして、地球の新しい見方や新しい世界を感じてもらえるかもしれないという期待感はあります。

―― 同じことの繰り返しになってしまいかねない日常において、毎日異なるかたちで、人とのつながりや世界とのつながりを感じられるということに可能性を感じます。
高谷 オフィスに通う生活のなかで、映像の中の風景が少しずつ変わっていることに気づいたりする。その気づきが、アートを面白いと感じてもらえることにつながるかもしれないですね。
―― 日々変化する作品だからこそ生まれる刹那的なコミュニケーションのような。
高谷 インターネットにおいてもスマートフォンにおいても、現代は「イメージ」が氾濫する世界です。つくられたものやコントロールされたもののなかで、映像や写真が本来的に持つドキュメンタリー性や一回性が失われつつある。一方で本作が扱う世界中の映像は「そこにある」というリアリティが如実に表れるものです。
―― ライブカメラ映像、ライブストリーミングコンテンツに共通する「生っぽさ」のようなものでしょうか。
高谷 そう、生っぽいんですよ。これらの映像は世界のどこかの今なのだと思うと、やっぱりちょっとドキッとする。「見てほしい」といった恣意性や、アートとしての意図がない映像であるということが重要だと思います。

メディアアートの可能性
―― これまで美術館や展覧会で作品を発表してきたDumb Type(ダムタイプ)にとって、今回のようなパブリックアートという形式は初の試みです。タイムベースのメディアアートを選んだことにも意味があると。
高谷 《WINDOWS》では小さなピクセルからなるLEDパネルを使っていて、そのメディアの特性を引き出せるような映像を収集しています。LEDパネルがパブリックアートのマテリアルになり得るのかという実験でもあるんです。絵画にはないメンテナンスや環境が必要とされるなかで、このメディアでしか表現できない世界の姿があるはず。
―― 時代や技術に合わせて新しいアートのアイデアが生まれるシーンに立ち会えたとき、自分が生きていることを実感します。ダムタイプの今後の展開も楽しみにしています。
高谷 メンバーそれぞれの活動が進み、そこでの知見が蓄えられていった先に、どこかのタイミングでまたダムタイプとして一緒につくることができたらと思っています。