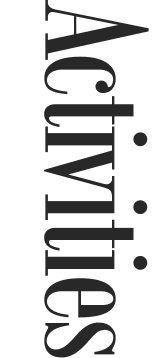
[ 武井祥平・高橋琢哉インタビュー③ ]
―― 「武蔵野の森」を受け継ぐ建築空間のあり方
WORK with ART Project 開発ストーリー

5年目の武蔵野の森
―― 改めて、ミュージアムタワー京橋のモチーフである「武蔵野の森」を、3階オフィスラウンジにどのように取り入れたのか、お話をうかがいたいです。
武井祥平(以下、武井) 21階から23階にあるスキップフロア型の屋上庭園は、都心の高層ビルでありながら自然を感じることのできる、このビルのユニークネスでもあります。武蔵野の森という原点を受け継いでいくうえで、竣工から5年目のビルを「5年目の武蔵野の森」に見立てるというコンセプトが、庭師の西尾耀輔さんとの対話のなかで立ち上がりました。そこから、生まれたばかりの森にはどのような木々が芽吹いていたのだろうかと想像を膨らませるようになりました。
高橋琢哉(以下、高橋) 森の気温は何度くらいで、日の出と日の入りは何時ごろなのか、どんな動物が暮らしているのかといった科学的な観点も交えながら、そこに広がる風景全体のイメージをチームで共有していきましたね。
武井 大きな平野に佇む5年目の若い森。そのような自然の広がりを感じ取れるような体験を、限られた屋内空間に生み出すために、その風景の一部を切り取った姿としての植栽を構想しました。

―― ビルそのものとの一貫性を意識されていたのですね。
武井 空間づくりに限らないあらゆる仕事において、物事の成り立ちを詳らかにしていくこと、ときには「なぜ存在しているのか」といったところまで立ち返るプロセスを大事にしています。そもそも建築の内部空間に人工的な緑を取り入れる意味とは何なのか、屋上庭園との関係性はどうあるべきかといった議論を重ねていきました。
高橋 両方のフロアで得た感覚が呼応する体験を、このビルで働く人に味わってもらいたいと思っています。音に耳を向けるという体験と、音が耳に入るという体験、そのどちらも揃った空間において、自分にしかない受け取り方や居心地の良さを探りあてて欲しいです。
余白が生み出す創造的な働き方

―― これまでのお話のなかで大事にされてきた「余白」や「自由」というキーワードは、働き方にどのような影響を与えるのでしょうか。
高橋 設備やロケーション、人間関係など、自分にとって必要な環境やストレスの要因が何なのかを問いかけること。自分の中の嘘を見逃さないことが重要です。そうした「心の中の自由」を確認することで、たとえ与えられた仕事であっても、自分なりの意味を見出し、新たなアプローチや発想を持つことができるのでしょうか。
武井 企業活動におけるイノベーションとは、目標や課題を定めること自体が難しい取り組みです。誰もやったことのない、スコープの定まらないものに向かうときには、職能という枠組みでは定義できない個性や特技が発揮される必要があると考えています。職能から「はみ出した」部分を許容することから、創造性が育まれるのではないでしょうか。