
[ ダムタイプインタビュー⑤ ]
―― “ありのままの世界”に向き合うためのアート

インターネットの本来像を問う
―― 《WINDOWS》は今後どのように展開していくのでしょうか。
高谷史郎(以下、高谷) このプロジェクトは、3年間を通じて段階的にアップデートを重ねるパブリックアートとして始まりました。現在は2026年に予定している第3弾の発表に向けて、構想を進めているところです。

《WINDOWS》は地球規模の環境や情勢とリンクしていて、日々この世界で起きている変化を映し出す作品です。これから地球がどうなっていくのか、楽しみでもあるし、心配なところもあります。たとえば、インターネットの規制が強まれば、ライブカメラの映像が使えなくなる可能性もあるでしょう。インターネットは世界がつながっていることの象徴であるはずなのに、近年はむしろ分断の要因になっているとも言われます。もっとフラットに、ひとつの考え方やビジョンを共有する手段としてインターネットを再解釈できるようになればと願っています。
資本主義が行き着く先では、差異を生むことが価値として重視され、何事も“早い者勝ち”の構造が広がっているように感じます。そうではなく、皆で一緒に全体のことを考えていけるような社会になってほしいと思うのです。
都市で感じる大自然のスケール
―― 一連の制作を通して、ご自身の地球の見方に変化はありましたか。
高谷 さまざまな場所の映像を見ていると、やはり自然はすごいと実感しますね。京都にあるダムタイプの拠点では《WINDOWS》のテストとして全周カメラを設置し、空をずっと眺めていました。大気の動きが意外と激しく、夕日も驚くほどきれいで、大自然の中に自分がいるんだという感覚が湧いてきました。ミュージアムタワー京橋の屋上に設置したカメラでも、空や空気の流れがよく分かります。東京のど真ん中でありながら、驚くような大自然を感じるんですよ。

古舘 健 ずっと映像を見ながら制作しているので、世界のどんな場所にどんなライブカメラがあるか、だいたい覚えてきました。プロジェクト当初、およそ2,500カ所のライブカメラから映像の取得を行うなかで、「画面に映っている景色は地球のどこかに確かに存在している」と思いながら作品をつくっていました。いつか旅先で、ライブカメラ越しに見た風景と同じ場所に出会ったら感動するでしょうね。「あの看板、見たことがあるぞ」と(笑)。
濱 哲史 第1弾では、とにかく新しい技術と新しい見方で世界を見るということに取り組んでいました。第2弾では、このミュージアムタワー京橋でしか得られないサイトスペシフィックな映像と音を取り入れたことで、作品がこの場所にとても近い存在になったと思います。《WINDOWS》が、このビルで働く人たちやビルの前を通り過ぎる人にとって、心の窓を開け放ってくれるような、そういう存在になればと思います。
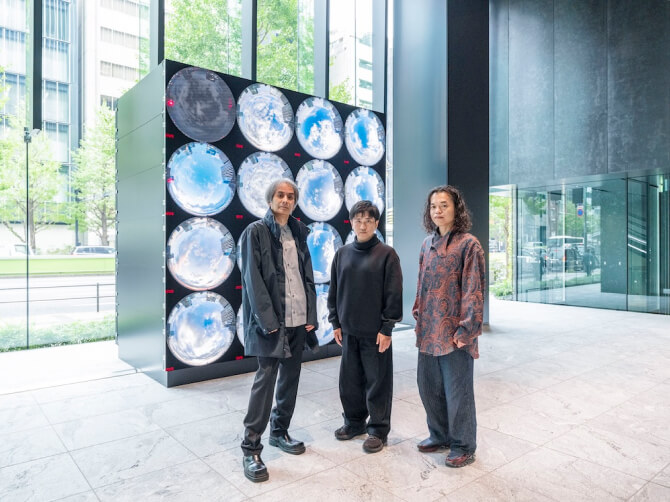
高谷 そこに映っているのは普通の日常であって、何も起こらない1日かもしれない。でも日常の日々というのは、別に特別なものではないですよね。多くの人が、なんとか特徴のある1日にしようと頑張るけれど、実はそれがストレスになっていないかと思ったりもします。濱君が言ってくれたように、窓を開け放してリセットする。アートとは本来そういう働きかけをする存在であるはずです。オフィスに絵が掛かっているのと一緒のこと。
人間の欲望が介在しない、何も起こらない風景がただ映し出され、日々が過ぎていく。そのことを感じられるだけでも、現代社会を生きる人々の心を整えてくれるのではないでしょうか。こうした“意図しないつくり方”というプロセスにも、《WINDOWS》がダムタイプらしい作品であることが表れているように思います。